

History
1899
甲斐和里子(旧姓・足利)は、松田甚左衛門の助力を得て、京都市下京区東中筋通花屋町上ルに顕道女学院を創立。(本学園の創始年)
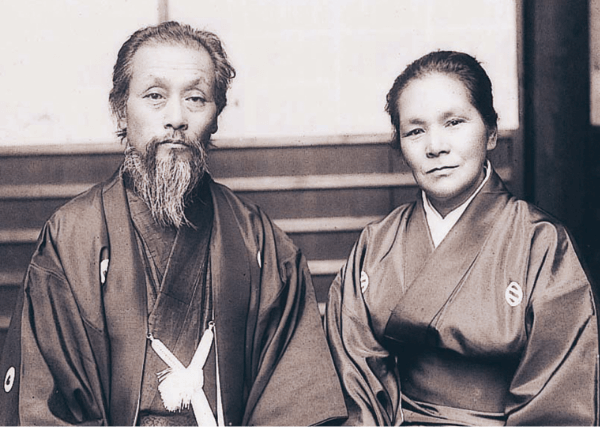 甲斐和里子(明1.6.15~昭37.11.27)左は甲斐駒蔵
甲斐和里子(明1.6.15~昭37.11.27)左は甲斐駒蔵
1900
顕道女学院創立の志と理念を貫くため、甲斐和里子は夫・駒蔵とともに、醒ヶ井五条下ルに文中園(のち文中女学校と改称)を開設。
1910
大谷籌子裏方(西本願寺門主大谷光瑞師夫人)、九條武子・仏教婦人会連合本部長らの尽力によって、矢部善蔵経営の京都高等女学校を買収し、「文中女学校」と合併。校名を「京都高等女学校」とする(この年を本学園の創立年としている)。
 大谷籌子(明15.11.5~明44.1.27)
大谷籌子(明15.11.5~明44.1.27)
九條武子(明20.10.20~昭3.2.7)
1911
矢部善蔵設立の京都商業女学校を合併。
京都商業女学校を「京都裁縫女学校」に改称。
1912
九條武子本部長らが
「女子大学設立趣意書」を発表。
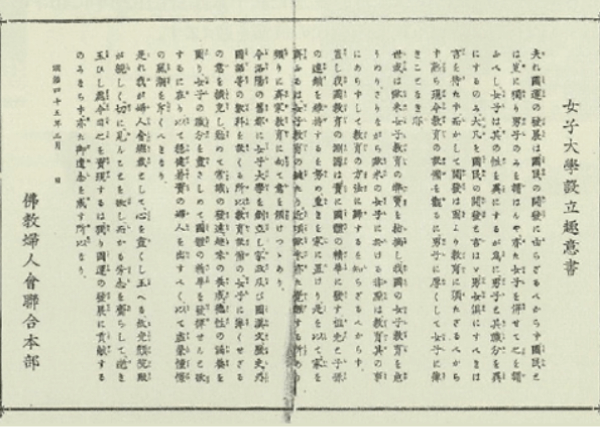 女子大学設立趣意書
女子大学設立趣意書
1917
「京都幼稚園」設置
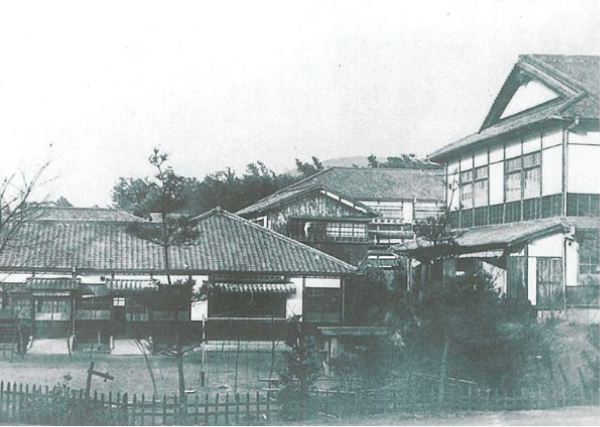 幼稚園設立当初の園舎
幼稚園設立当初の園舎
1920
「京都女子高等専門学校」(京都女子大学の前身)開学
大谷家より寄贈を受けた「錦華殿」の移築完成
1924
貞明皇后(大正天皇の皇后、大谷籌子裏方の妹君)が行啓され、「あたたかに、そして香りゆかしき心の学校である」とのお言葉をいただく。
以来、本学園は「心の学園」とよばれるようになった。
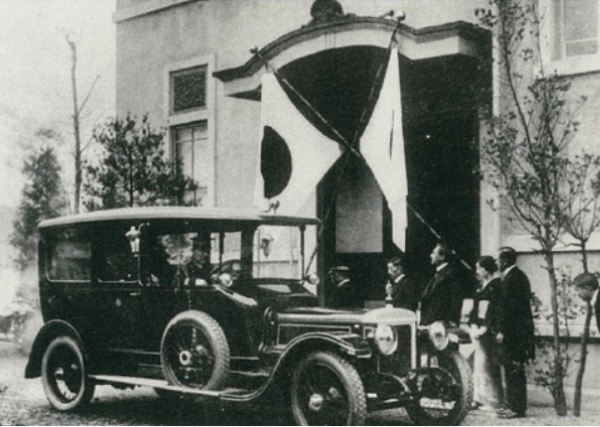 貞明皇后行啓
貞明皇后行啓
1944
財団名称を財団法人龍谷女子学園に改め、女専、高女、裁女、保姆養成所の設置主体となる。
京都女子高等専門学校を京都女子専門学校と改称。
京都裁縫女学校を廃止して、京都女子商業学校を設置。
1947
「京都女子中学校」開校
1948
高等女学校、女子商業学校を廃止し、「京都女子高等学校」開校。
1949
「京都女子大学」(文学部国文学科・英文学科・中国文史学科、家政学部食物学科・被服学科・児童学科)開学
 開学まもない頃の授業風景
開学まもない頃の授業風景
1957
「京都女子大学附属小学校」開校
新校舎竣工
1学級42名で発足
 第1回入学式
第1回入学式
1962
校歌制定
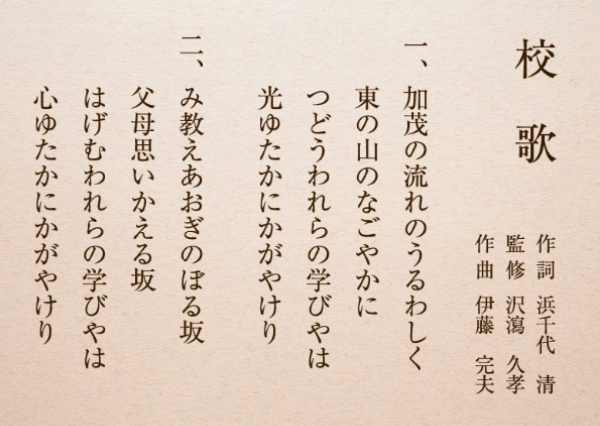 校歌
校歌
1963
第1回卒業式
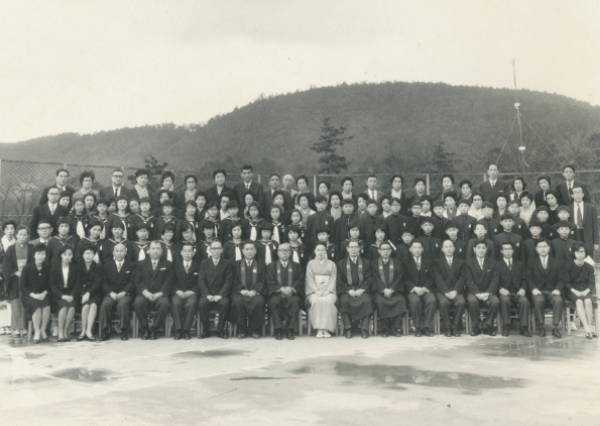 第1回卒業式
第1回卒業式
1967
校舎移転(旧中学校)
1969
詩の研究会(研究発表)
1976
附属小学校舎竣工
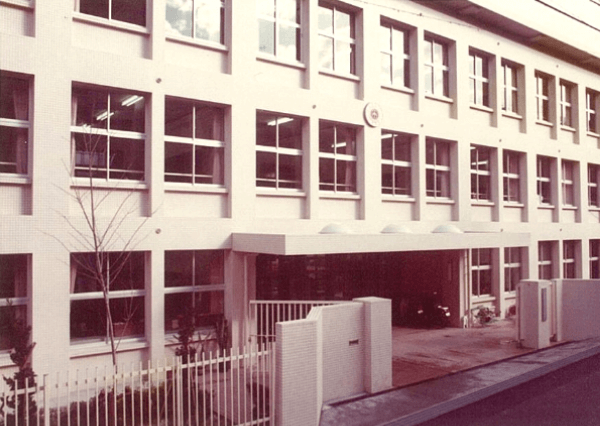 附属小学校舎
附属小学校舎
1977
西日本私立小学校連合会 / 研修会場
1987
附小教育研究会発表会
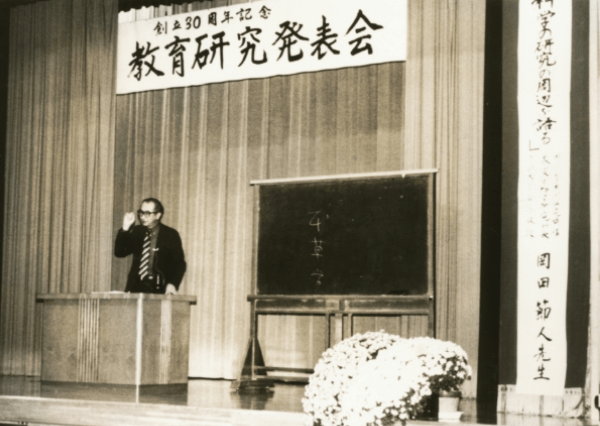 附小教育研究会発表会
附小教育研究会発表会
1991
附小教育研究会発表会
1992
研究誌「読んでわかる参観日」出版
1997
「卒業生名簿」作成
2003
西日本私立小学校連合会 / 研修会場
2007
創立50周年記念教育研究発表会
2008
校舎リニューアル
 附属小学校舎
附属小学校舎
2009
1~4年生 2学級編成
5、6年生 3学級編成
2010
学園創立100周年
京都女子学園創立100周年記念教育研究発表会
教育研究会
「国語力は人間力」(明治図書)出版
「京女式ノート指導術」(小学館)出版
2011
「京女式ノート指導術2」(小学館)出版
2012
「京女式対話で学び合う小学校古典」(明治図書)出版
「京女式しつけ術」(小学館)出版
2013
「京女式 板書・発問術1・2・3年」(小学館)出版
「京女式 板書・発問術4・5・6年」(小学館)出版
「京女式 ほめほめ言葉」(小学館)出版
2014
学校給食開設
2015
アフタースクール(希望者対象)開設
2017
教育相談室開設
2018
附小創立60周年
教育研究発表会
2020
学園創立110周年
授業を語る会
「国語の板書指導」(小学館)出版
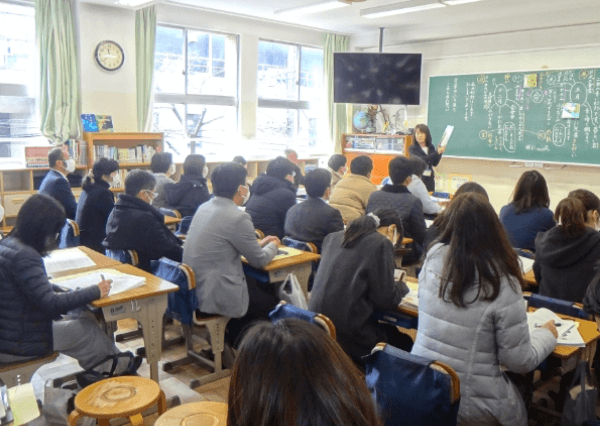 授業を語る会
授業を語る会
2022
新入児童の募集定員を80名から60名に減員。
2023
週5日制導入
スクールカウンセラー導入
2024
1〜6年生の教室に、ホワイトボード、プロジェクター設置
インスタグラム開設
 ホワイトボード
ホワイトボード
2025
40分6時間授業 開始
アフタースクール新コース開設
海外研修(台湾、シンガポール)開始
イングリッシュキャンプ(4年生)開始
広島 宿泊学習(5年生)開始